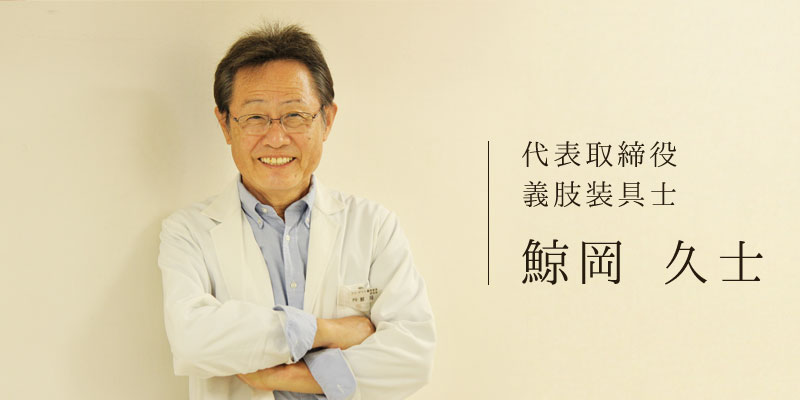
靴文化である欧米に比べ、靴を脱ぎ履きする習慣がある日本では、自分の靴や足のことを重視している方はまだまだ少ないのではないでしょうか。そのため靴が合ってなくても、「まだ若いから」「まだ歩けるから」「まだ履けるから」と思っている方も多いと思います。年齢を重ねるとともに足変形も進み、痛みがでてきた頃には、たちまち歩けなくなってしまい、歩けなくなると外出することも億劫になり気持ちも沈んできてしまいます。「もっと早く自分の足や靴のことを考えればよかった・・」と弊社にお越しいただく多くの方が口にされます。
私は約50年間にわたりこの仕事に従事してきました。また弊社を創業して23年目に入りました。
その中では色々な障害をお持ちの方々と接し、生活改善のお手伝いをさせていただきました。
私自身小児麻痺の疾患があり、長い間医師や看護師、訓練のさまざまなスタッフの方々にたいへんお世話になり今に至っています。
その経験から気持ちよく「歩く」ということで世界観を拡げ、自信につながり、そのことがいかに大きな喜びになるかということを身をもって感じ、この仕事を選びました。足にトラブルや障害はあっても、外出をひかえることなく、毎日明るい気持ちで過ごしていただきたいと思います。
歩くこと、すなわち靴や装具の重要さを痛感し、自分と同じような悩みをお持ちの方の手助けになりたいと思い起業し、23年目になりました。医療用の靴も「ものづくり」には変わりません。
常により良いものを作っていきたいと思っております。弊社に来られたお客様の痛みの原因を一緒に考え、より良い生活を送っていただくためにお作りします。
